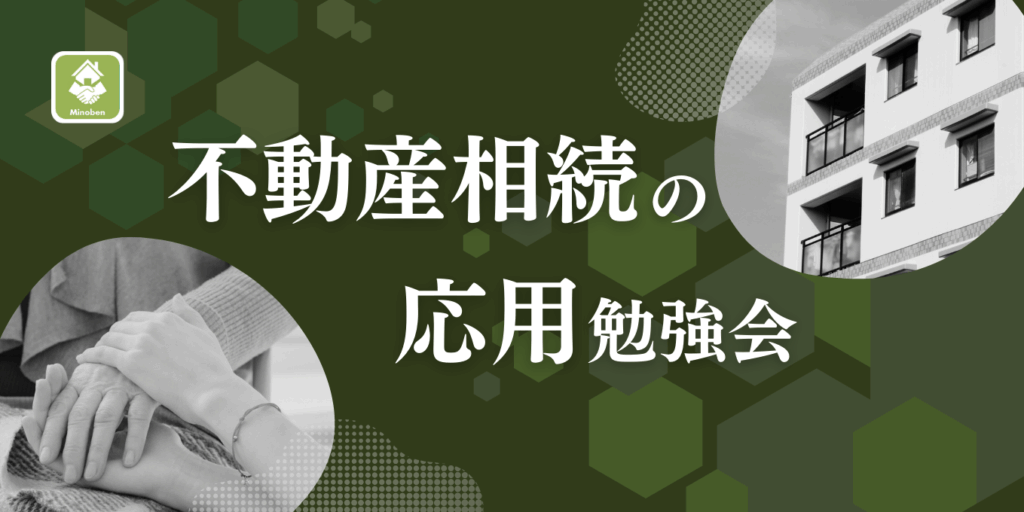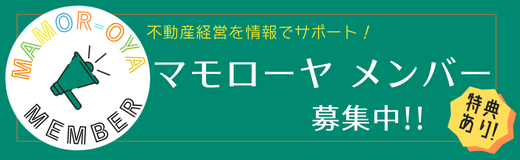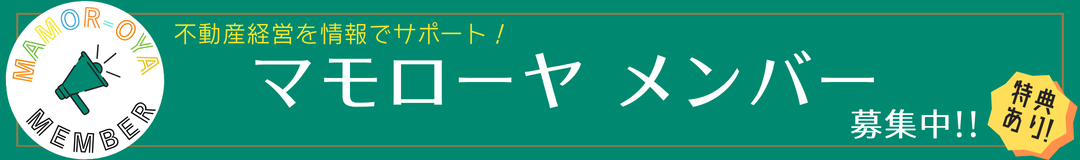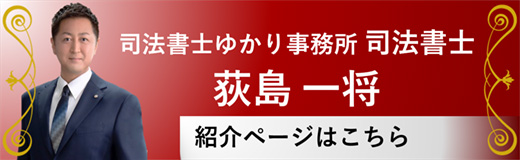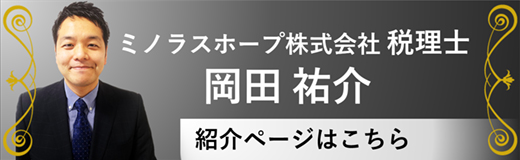お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

相続人間でもめている、もしくはもめる可能性が非常に高いことから遺産分割の話し合いから早く
解放されたいと考える人も多いと思います。
そのようなときのひとつの手段として「相続分の譲渡」が考えられます。
相続は権利主張がメインに考えられるところもあり、その権利を渡すという行為は珍しいのであま
り馴染みのない言葉ですが、今回はあえて取り上げさせていただきます。
相続分の譲渡とは
まず相続分の譲渡とはということから説明します。相続分の譲渡には以下のような特徴があります。
- 相続分の譲渡は自分がもらう財産の譲渡ではなく、相続人の地位そのものの譲渡
- 相続分の全部だけでなく、一部でも譲渡可能
- 譲渡先は他の相続人だけでなく、第三者であっても可能(複数人でも可能)
- 有償でも無償でも可能
- 他の相続人の同意は不要
ご注意いただきたい点としては、財産の譲渡ではなく、地位の譲渡となりますので例えばご自身の
相続分が1/4であった場合にはその1/4を譲渡するというイメージとなり、分割協議がまとまってしまう
と対象が地位ではなく、財産になってしまうためできなくなってしまうという点になります。
それ以外は比較的自由度が高いため、もめてしまいそうな相手に対して一部を譲渡することや全て
の権利を均等に他の相続人に譲渡するといったことも可能となります。
相続分譲渡の課税関係
上記の通り自由度の高い行為であることか想定されるケースも多いですので、譲渡先と有償無償の
ケースごとに解説をしていきます。
1.譲渡先:相続人、対価:無償の場合

相続分の全部を譲渡した場合には、相続税は課税されません。
相続分の一部を譲渡した場合には、譲渡しなかった部分に対して相続税が課税されます。

譲渡を受けた人の固有の相続分に譲渡を受けた相続分を加えたものに対して相続税が課
税されます
2.譲渡先:相続人、対価:有償

その相続分の譲渡に関する譲渡対価に対して相続税が課税されます。

譲渡を受けた人の固有の相続分に譲渡を受けた相続分を加え、そこから譲渡対価を控除したものに対して相続税が課税されます。
無償との違いは対価が発生しているため、譲渡側は対価相当が相続財産となり、譲受側は相続財
産から差し引かれる形となります。
3.譲渡先:第三者(自然人)、対価:無償

相続人以外に相続分を譲渡した場合には譲渡した人に相続税が課税されます。また、申告期限までに遺産分割が確定するかどうかにより手続きが異なりますので注意が必要となります。

譲渡を受けた相続分に対して贈与税が課税されます。
相続税の課税ではないので注意が必要です
4.譲渡先:第三者(自然人)、対価:有償

第三者に対する有償譲渡の場合には相続税だけでなく所得税にも影響します。
A.相続税の取扱い
無償と同様に譲渡した人に相続税が課税されます。
B .所得税の取扱い
有償での譲渡の場合には譲渡した人に譲渡所得税が課税されます。
ただし、相続分の譲渡は土地、建物、有価証券というような個々の財産の譲渡ではないので分離課税で
はなく総合課税の譲渡所得となるため、給与や他の不動産所得などと合算されてしまいますので所得状
況によっては税率が高くなる可能性があります。
また、譲渡収入から差し引かれる取得費については規定がないことから0円として考える可能性もあり、
専門家の判断により異なる可能性があります。

対価を支払っているため、時価よりも著しく低くなければ相続税も贈与税も課税されません。
5.譲渡先:第三者(法人)、対価:無償

A.相続税の取扱い
譲渡した人に相続税が課税されます。
B.所得税の取扱い
法人に対する贈与であることから譲渡した人に譲渡所得税が課税されます。

譲渡を受けた相続分の時価が利益として計上され、法人税が課税されます。
法人は相続税の対象外になるため相続税は課税されません。
6.譲渡先:第三者(法人)、対価:有償

④と同様の課税関係となります。
ただし、対価の金額が時価よりも著しく低い場合には時価による譲渡とみなされる可能性があります。

対価を支払っているため、時価よりも著しく低くなければ法人税の課税はされません。
適正な対価を設定するためには相続財産の把握が必要となりますので、
有償による場合には相続発生からある程度時間が経った状況になるかと
思います。
代わりに相続人間の状況も把握できるかと思いますので相続開始前で
の決断を迷っている場合にはよいタイミングなのかもしれません。
いずれにしてもご自身の財産状況を整理しておけば、争ってでも権利を得たいと考えていない次世代の方にも選
択の幅が出るかと思いますので本コラムがよいきっかけになることを願います。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
岡田 祐介
ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。