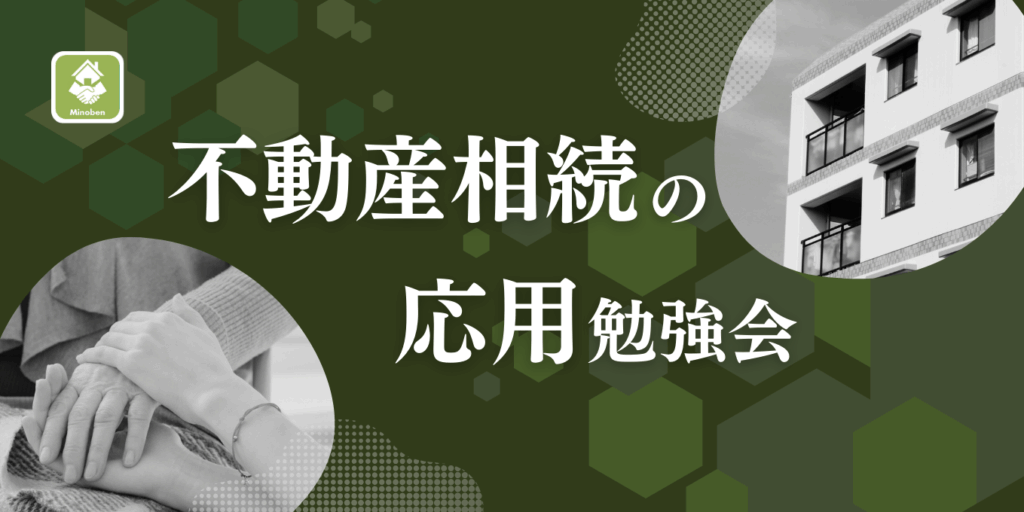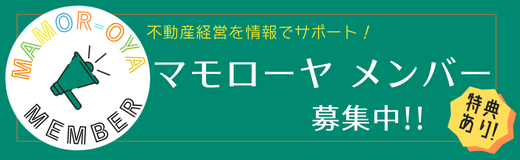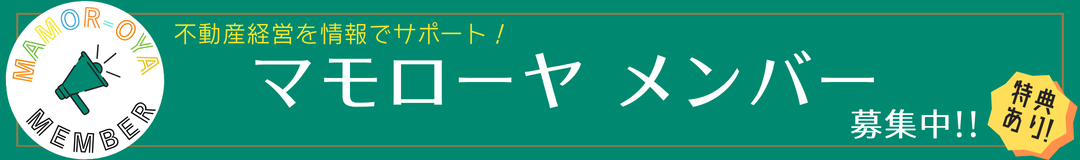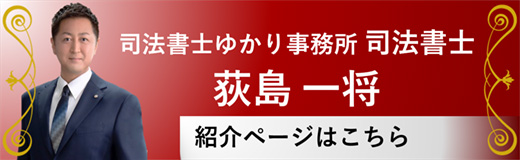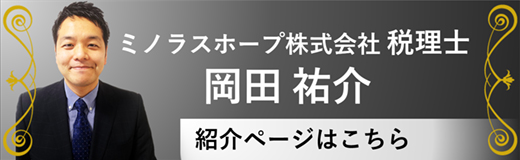お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将
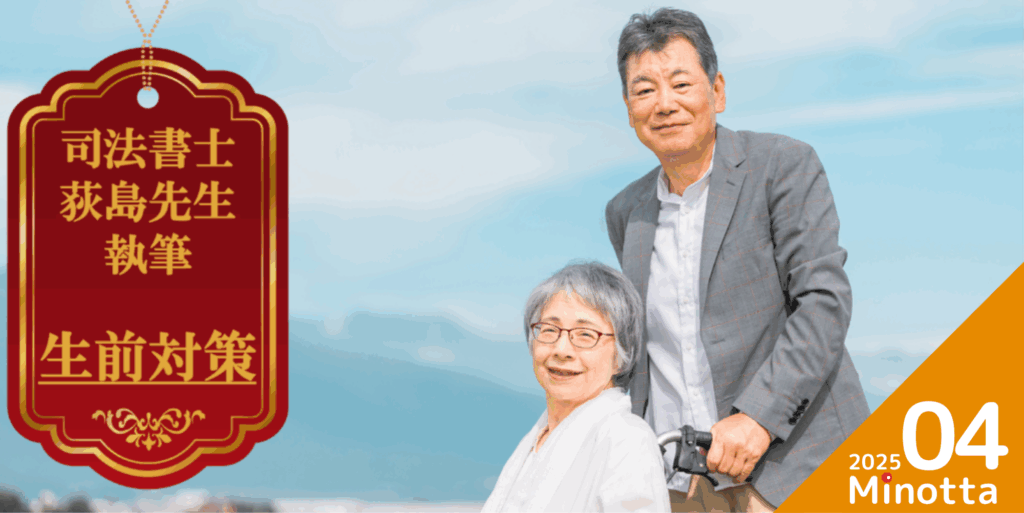
被相続人(亡くなった方)に子がいらっしゃらず、被相続人のご両親もすでに他界されているといった場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となることがあります。今回は、兄弟姉妹が法定相続人となるケースについて検討し、遺産相続における注意点や、生前にしておける対策について考えてみたいと思います。
相続順位は法定されている
被相続人の財産を相続する権利を持つ人は法律で決められていて 、その人のことを「 法定相続人」といいます。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外で法定相続人となる方の順番も法定されており、第1順位は、被相続人の子です。子がいない場合は、第2順位として直系尊属(両親、両親がいない場合は祖父母)が相続人となります。被相続人に子がおらず、両親・祖父母とも他界している場合は、第3順位として、被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)が相続人となります。
子や両親がいても兄弟姉妹が相続人となるケースも
また 、被相続人の子や父母がご存命であっても、被相続人が債務超過であったなどの理由で、子や父母が順次、相続放棄の申述を家庭裁判所にした場合、それが受理されると、兄弟姉妹が相続人となります。その場合、多くは相続人となった兄弟姉妹も相続放棄の申述をする必要があると思いますので注意が必要です。そうしたケースでは兄弟姉妹は、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に 、相続放棄の申述をする必要があります。
兄弟姉妹が相続人である場合に必要な戸籍等
相続手続をする際には、原則として被相続人出生から死亡までの戸籍や相続人の現在の戸籍を収集する必要があります。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、これらに加え、相続関係者の状況によって 、両親の出生から死亡までの全戸籍や、祖父母の死亡の記載のある戸籍、兄弟姉妹がなくなっている場合は、その出生から死亡までの戸籍など、かなり多くの戸籍を取得することになります。
生前対策として考えられること
被相続人の配偶者というのは、必ずしも被相続人の兄弟姉妹や甥・姪との関係が良好であるとは限りませんし、たとえ良好であったとしても、死亡後の財産の分け方について、ざっくばらんに話し合え
るような関係を期待できることの方が稀だと思われます。配偶者の死亡後に、ただでさえ悲しみと不安にさいなまれる中で、配偶者の兄弟姉妹または甥・姪と、遺産について協議をするのは大変、厳しい作
業となり得ます。
そこで、ご自身の兄弟姉妹が相続人となることが分かっている場合には、生前に相続について対策しておくことが重要です。まずは 、ご自身の推定相続人(法定相続人となる方)を確認しておくことが必要 となります 。そして 、ご自身の財産について生前に洗い出し、誰にどのような財産を残すのかを検討して、有効な遺言を作成しておくことは最低限、必要な作業といえるでしょう。
兄弟姉妹には遺留分(法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分)が認められませんので、遺言を作成しておくことで、相続開始後のトラブルを少しでも未然に防ぐことが可能となります
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言などの生前対策がより重要となります。必要な手続や方針については、専門家に相談しながら、生前対策や相続手続を進めていくことが重要です。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。