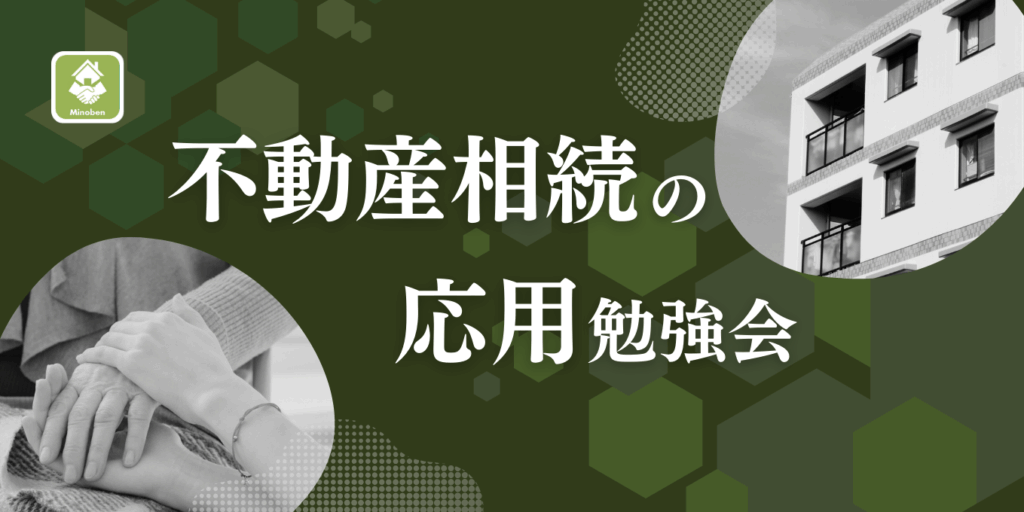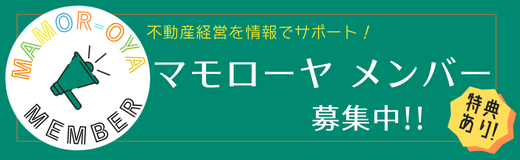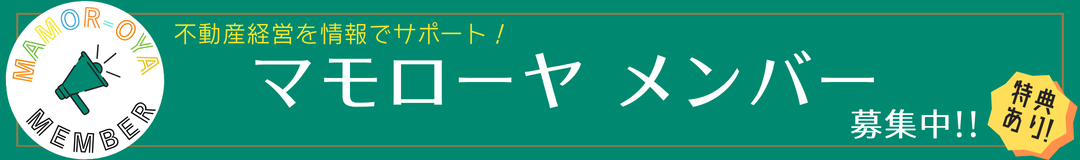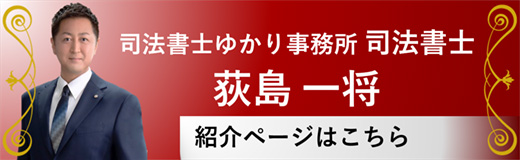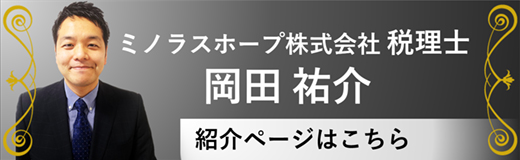お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

税制改正大綱の発表がありましたのでこちらをテーマとしていきます。今回の改正も不動産オーナー様に関しては直接的な影響は少ないものといえます。そのため個人の所得税や防衛増税を中心に解説をしていきます。
1. 基礎控除、給与所得控除の見直し(年収103万円の壁)
各メディアでも報道されていた年収103万円の壁に関する改正です。基礎控除が合計所得金額に応じて下の表のように見直されます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超、2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超、2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超、2,500万円以下 | 16万円 |
2,350万円以下の方は控除額が10万円増えることとなります。
また、給与所得者の給与額から控除される給与所得控除額についても、現行55万円の最低保障額を65万円に引き上げることとされています。これにより、所得控除額を20万円引き上げることで123万円までは所得税が課税されないこととなります。
今回は社会保険での130万円の壁の範囲内としていますが、大綱には「178万円を目指して、来年から引き上げる。」と明記されていました。結果的に手取りがどうなるかという部分については、先送りという感じでしょうか。
2. 特定親族特別控除(仮称)の創設
人手不足対策として、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子が給与年収150万円までは、現行の特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられ、また、これを超えた場合でも控除額が段階的に減るものの所得控除を受けることができる制度が新たにできます。
所得控除額については、下の表のようになります。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超、85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超、90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超、95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超、100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超、105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超、110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超、115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超、120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超、123万円以下 | 3万円 |
適用対象者の要件は下記になります。
- 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色専従者を除く)
- 合計所得金額が123万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
③は扶養控除とのダブル控除はなしという意味になります。
2024年10月から社会保険加入義務の見直しにより、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトも適用対象となりました。従業員要件に「学生ではないこと」が含まれているので、1の改正とは違い、学生であるお子様については追い風かと考えられます。
3. 扶養親族等の所得要件の緩和
1と2の改正に伴って配偶者控除や扶養控除における所得要件が48万円から58万円に引き上げられています。
4. 生命保険料控除の拡充
前年の大綱で見直しが検討されていると明記されていた、子育て世代(23歳未満の扶養親族を有している場合)への生命保険料控除は予定通り盛り込まれています。ただし、一般生命保険と介護医療保険と個人年金の適用限度合計額は現行の12万円から変更しないという部分も予定通りでしたので、バランスよく生命保険に加入されている方からすると影響がなさそうです。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超、60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超、120,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
5. 防衛特別法人税(仮称)の創設
防衛費の財源確保として法人に対する税金が令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。
中小法人を除外する記載はないためすべての法人が対象となりますが、基礎控除額が設定されています。基礎控除額は500万円になりますが、税額計算の基礎は法人税額となっておりますのでザックリとした金額として 利益が2,600万円を超えた事業年度はと発生する可能性が高いとお考えいただければと思います。税率は4%ですので基礎控除額を超えた金額にこれを乗じることとなります。
不動産賃貸業のみで当該金額を超えそうであれば、相続人の人数にもよりますが相続対策のひとつとして物件を保有する法人を増やすという検討も必要かもしれませんし、物件を売却する際に売却価額と簿価によっては対象になる事業年度もあるかと思いますので、事前に保有物件の修繕の前倒しなども考えなくてはいけないかもしれません。防衛費に関しては個人課税への影響があるかどうか不明確ではありますが、大綱に記載されている検討事項に文言はありませんでした。
当然楽観視はできないかと思いますので、変化があればまたお伝えできればと考えております。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
岡田 祐介
ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

.png)