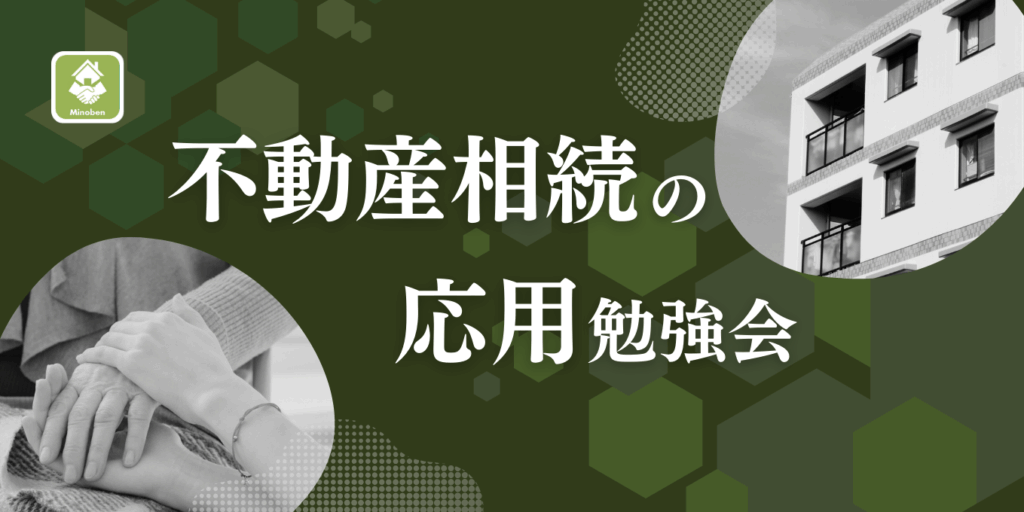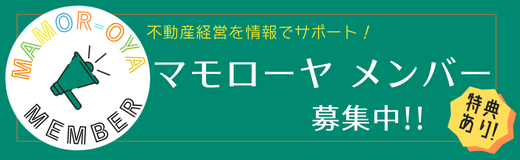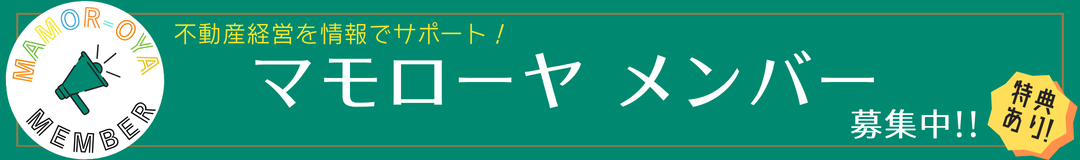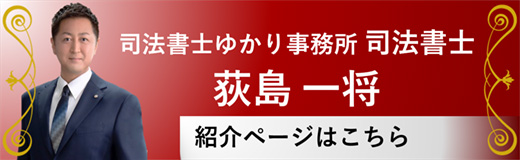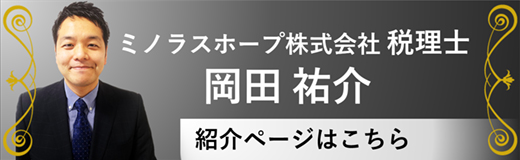お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

認知症の診断を受けたすべての人が即、意思能力がないと判断されるわけではありません。しかし、相続人が認知症となり恒常的に意思表示ができなくなった場合、そのままでは相続手続を進めることはできません。遺産分割協議や相続放棄等の相続手続は、相続人の意思表示によるものですので、相続人が意思表示できない限り、手続を進めることができないというわけです。
被相続人の債務超過が明らかな場合など、相続放棄をすべきと考えられるときでも、認知症の相続人は相続放棄をすることができないのか、というと、別途手続を経ることで相続放棄が可能となることがあります。
今回は、認知症の相続人が相続放棄をする場合にどのような手続が必要となるのか、ということについてお伝えします。
相続放棄の期限は原則として3か月以内
相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を全て放棄することで、家庭裁判所に申述する方法で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされるという強烈な効果がありますので、非常に注意が必要で、単にプラスの財産を他の相続人に承継させたいという場合、通常は相続人の間で遺産分割協議により行うことが一般的です。
ただ、被相続人が債務超過で、それを承継すると相続人自身の生活がままならなくなるという場合には、相続放棄を選択することになると思います。
相続放棄の申述は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して行う必
要があります。この期間を「熟慮期間」といい、その3か月間の間に、相続放棄をするかどうかを熟慮する、という意味が込められています。
意思表示ができない人の相続放棄
認知症である相続人は、ご自身で意思表示ができなくなってしまうと、そのままでは相続放棄をすることができません。認知症の相続人が相続放棄をしなければならない場合は、成年後見制度の利用を検討することになります。成年後見制度を利用すると、認知症である相続人のために成年後見人を付し、認知症である本人に代わって、当該成年後見人が、相続放棄の申述を行うことになります。
成年後見人を選任するための準備から家庭裁判所に申し立て、選任されるまでに通常、数か月程度かかりますが、成年後見人による相続放棄をする場合には、当該成年後見人が認知症である本人のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄を申述することができる、とされていますので、後見人が選任されるまでは、熟慮期間は進行しません。
成年後見制度を利用した場合の注意点
成年後見制度を利用する際には、注意が必要です。成年後見制度は、現行(2025年3月時点)ではいったん開始すると認知症がすっかり治ったなどの事情がない限り、原則として途中でやめることができません。成年後見人が付されると、生涯、本人の財産管理や契約行為等は成年後見人が行うことになります。家族でない人が成年後見人となれば通常は報酬も発生することになると考えられますので、その負担も生涯にわたって続くことになります。
ご本人にとっては、財産管理がきちんと行えるという反面、金銭的負担も生じる話ですので、十分に
検討する必要があります。
認知症となると、意思表示を要する手続がすべて滞ってしまうリスクがあるため、相続に係る生前対策とともに、認知症対策を行っておくことは不可欠です。高齢社会において、今後も特に重要となってくるでしょう。信頼できる専門家に相談しながら検討することをおすすめします。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
荻島一将
司法書士・行政書士ゆかり事務所 所属の荻島一将(おぎしま かずまさ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続対策や生前対策について、わかりやすく執筆・解説いただいています。