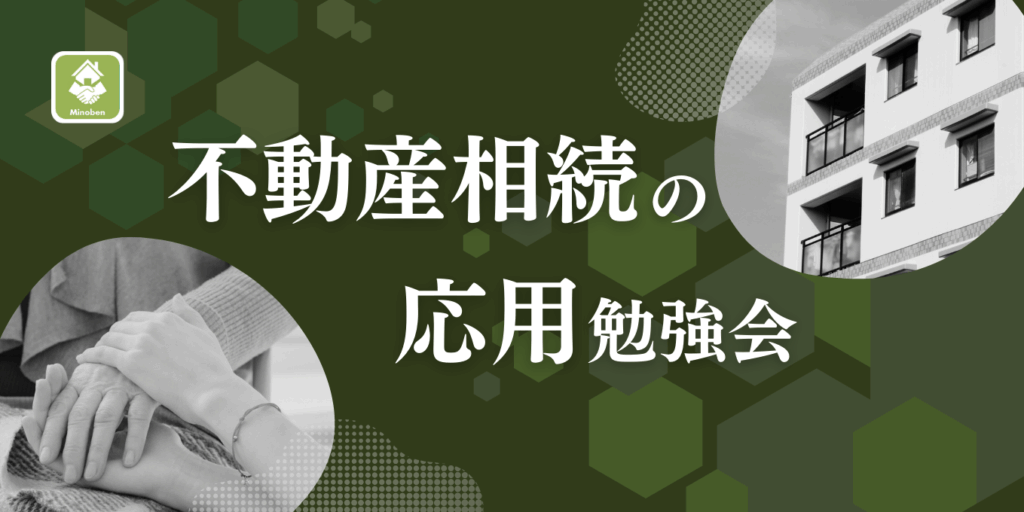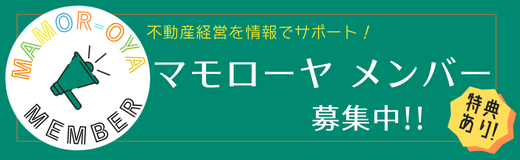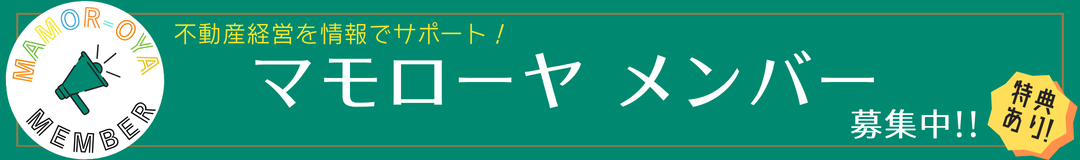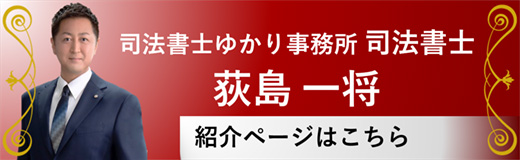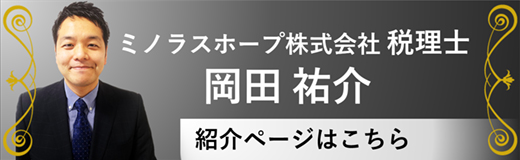お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

過去の本コラムでも、何度か取り上げている名義預金。相続人が亡くなってから、子や孫が自分名義の預金があることを知ったというなら典型的な名義預金となります。しかし、「生前からその存在を知っていて、使おうと思えば使えていた」という場合に判断が必要となります。過去にも記載した通り、その抗弁にはそれなりの労力を要します。
ただ、贈与をしっかり成立させたとしても、親の心情としては大金を贈与することによって、子や孫の金銭感覚を狂わせたくないという気持ちもあるかと思います。
そこで今回のコラムでは、名義預金について家族信託を活用する方法をお伝えします。
1.家族信託に関する用語
家族信託を活用すると、口座の管理はご自身のまま、贈与も成立させることが可能となります。下記の状況を例に、具体的に説明します。

信託では、信託財産となる財産を提供する者を「委託者」といいます。その対象となる財産の所有権を、①財産から利益を受ける権利 ②財産を管理・運用・処分できる権利の2つに分け、これら①の権利を有する者を「受益者」、②の権利を有する者を「受託者」といいます。
委託者と受益者が一致している場合を自益信託といい、今回の例のように委託者と受益者が一致していないものを他益信託といいます。
他益信託は、読んで字のごとく自分でない他の者に利益のある信託です。そのため、他益信託の場合、「信託財産は委託者(Aさん)から受益者(Aさんの孫)に贈与されたものである」と税務上はみなされます。
2.家族信託を活用した場合のメリット
信託でない通常の贈与の場合、贈与を受けた受贈者が、その贈与を受けた財産の管理・運用・処分の権利ももつこととなります。しかし、民事信託の場合、その権利を委託者に渡す契約になるため、財産の名義は受託者であるAさんの長男となります。このように、孫が自由に金銭を使えなくとも、金銭は孫のものとして考えることができるのです。
さらに、先述の通り、信託契約は委託者(Aさん)と受託者(Aさんの長男)の間で締結される契約です。そのため、受益者(Aさんの孫)には、金銭が贈与されたことを知らせないという状況も可能なのです。
このように信託契約をすることにより金銭感覚を狂わせてしまうかもしれないなどの不安を払拭することができ、かつ、贈与も適切に成立させることができるのです。
また、受託者を法人にすることも可能なため、資産管理会社を既に設立されておられる方はこちらも選択肢として使えます。
3.注意点 信託財産が110万円以上の場合
ただし、信託財産が110万円を超えた場合、信託契約をした時に「祖父から孫に対する贈与」とみなされ、孫が贈与税申告をする必要があります。そのため、信託財産を追加していく方式など、どのように信託を設定していくかが重要となります。
このように、家族信託を活用するには専門的な知識が必要です。ご検討される場合には、はじめに、家族信託に強い司法書士や行政書士、税理士等の専門家へ相談することを強くおすすめします。
流れとしては、専門家に家族信託契約の文案の作成を依頼し、法務上・税務上の問題がないか、委託者の意向に合致しているか等を確認した上で、公証役場において公正証書にするとよいでしょう。家族信託は、公正証書にしなくても契約は成立します。しかし、受託者が受益者のためにのみ運営する受託者名義の口座である信託口口座を開設する際に求められることがあるため、金融機関への事前説明を行い、公正証書や必要書類を確認しておくことも重要と言えます。
信託はとっつきにくいもので税務上のメリットが大きいものではないため、手間だけを見ると敬遠されてしまうのではと感じています。そのなかでも使い方・考え方によっては皆様の望む相続のスタイルに合う可能性もあるかと思いますので今回ご紹介させていただきました。
相続対策はオーダーメイドです。ほかの方の行った方法がご自身にも当てはまるかどうかということから考え始めてはいかがでしょうか。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
岡田 祐介
ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

.png)