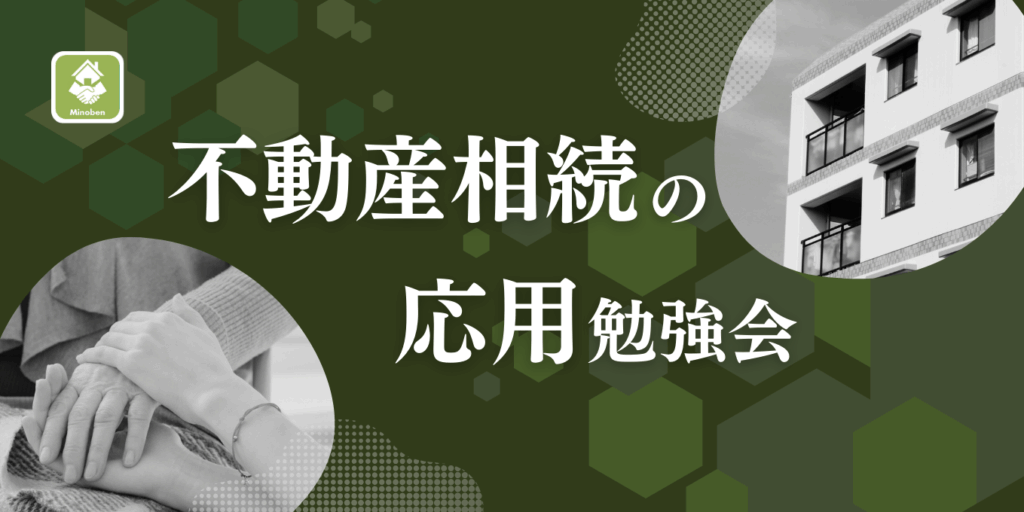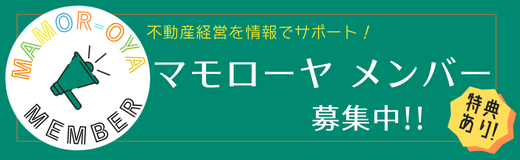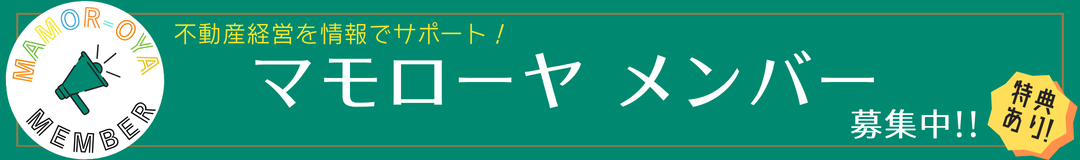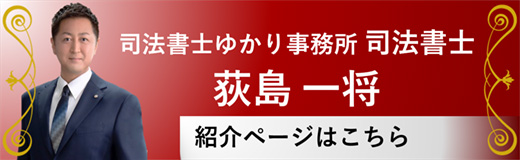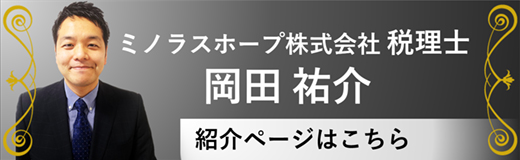お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

ここ数年でIT技術を筆頭に、私たちを取り巻くモノや環境は大きく変わってきています。そんな中、ご自身のご年齢とともに「住環境も変えていきたい」という方も少なくないと思います。特に、相続というトピックは環境を変化させるひとつの引き金とも言えるでしょう。保有しているご自宅や物件を売却して、別の地域に引っ越す。介護等の不安から、お子様のお住まいの近くに引っ越す。といったことも起こってきます。
こういった際に気を付けていただきたいのが、小規模宅地の特例の適用要件である居住継続要件・事業継続要件・保有継続要件などです。そこで今回は、相続した物件の売却等に関してお伝えしたいと思います。
居住継続要件と保有継続要件
宅地の評価額を大きく減額してくれる「小規模宅地の特例」は、ご存じの方も多いかと思います。特定居住用宅地等の場合には330㎡という制限はありますが、評価額の80%相当の減額を受けることができるため、税金によってご自宅を手放さなくてはならない状況を回避できる制度です。それだけ評価額への影響が大きい制度ですので、だれでも無条件に受けられる訳ではなく、要件が設定されています。それが、居住継続要件と保有継続要件です。
居住継続要件
相続した人が、相続税の申告期限まで引き続きその自宅に住んでいること
保有継続要件
相続した人が、相続税の申告期限まで引き続きその自宅を持っていること
相続した人が配偶者である場合、この要件を満たす必要がなくなり、相続後すぐに自宅を売却してしまっても小規模宅地の特例の適用を受けることが可能です。ただし、申告期限前に売却してしまうと、当該売却額が相続税申告における当該土地の評価額(時価)であるとされる可能性が高くなります。そのため、よほどのことがない限りおすすめはしません。
具体的に考えてみましょう
上記を踏まえて、2つのケースについて小規模宅地の特例が適用されるのかを考えてみましょう。状況は人それぞれですが、これらの例も参考にしていただけますと幸いです。
ケース1
- 土地取得者・・・配偶者
- 土地の利用状況
生計一親族である長男が一人暮らしをしていたが、相続発生後に引っ越すことに。 - その他
被相続人夫婦の居住用敷地は別の場所
相続税の申告期限前にこの土地を売却した場合、小規模宅地の特例の適用は可能なのでしょうか?
答えは、適用可能です。「配偶者は住んでいないのに、どうして特例が適用されるのか?」と、疑問を持つ方もいるかと思います。配偶者については、被相続人の居住用だけでなく、配偶者が住んでいない被相続人の生計一親族の居住用を取得した場合にも、小規模宅地の特例が適用でき、保有継続要件もありません。
「配偶者が大いに優遇されている」と感じるかと思いますが、配偶者に保有継続要件がないのは居住用宅地のみです。事業用宅地(特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地・貸付事業用宅地)については、他の相続人同様に保有継続要件がありますので、「配偶者が亡くなったことで住む場所を失わないための配慮」と、お考えいただけるとよいでしょう。
ケース2
- 保有継続要件がある宅地等(事業用宅地や配偶者以外が取得した居住用宅地)について、申告期限前に売買契約を締結した場合
下記2パターンが考えられます。
① 申告期限前に引き渡しを行ったとき
申告期限前に売買契約を約定し、申告期限前に売却してしまった場合、保有継続要件を満たしたとはいえません。よって、小規模宅地の特例の適用はできません。
② 申告期限後に引き渡しを行ったとき
売買契約自体は申告期限前ですが、引き渡しが申告期限後となっているケースです。不動産の譲渡は、引渡日に所有権が移転すると考えます。つまり、引き渡しが申告期限後の場合、申告期限前に売買契約をしていたとしても保有継続要件を満たしていることとなります。よって、小規模宅地の特例の適用は可能となります。
よく耳にするような特例であっても、相続は人それぞれの事情があります。小さな違いだと思っていても、大きく影響を及ぼすことがあるのでご注意ください。代々続く不動産にも、「存続」以外の選択肢が相続にはあると思います。本コラムが、様々な選択肢をお考えの中で、よりよい結論になるお手伝いになれば幸いです。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
岡田 祐介
ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

.png)