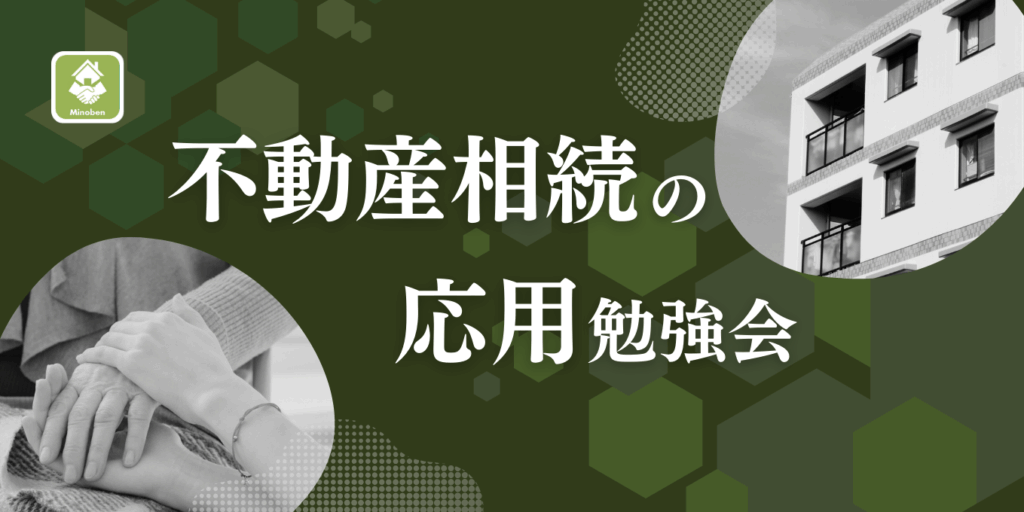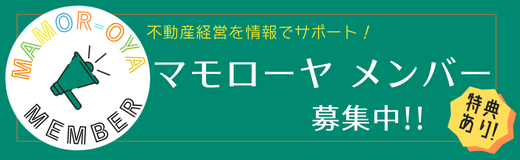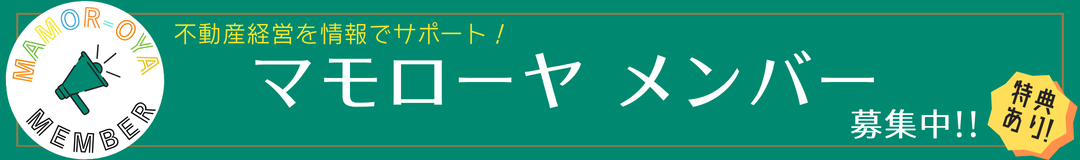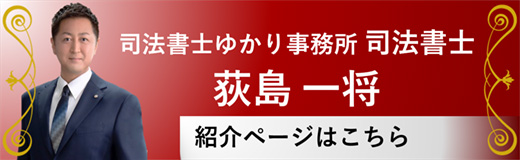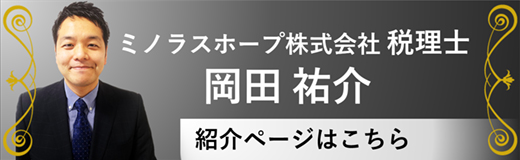お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

おでかけの際に、地図アプリを利用する方が増えています。最近は、その精度が高くなってきていますが、実際に歩いてみると、「距離は近いのに坂道がきつかった…」と経験されたことはありませんか?実は、こういった高低差は土地を評価する際にも加味されるものです。そこで今回は、高低差のある土地の評価についてご紹介したいと思います。
1.高低差がある土地の評価額
高低差がある土地に該当した場合の評価額への影響は、高低差がないとした場合に算出した評価額から10%減額となります。
これは国税庁ホームページに掲載されているタックスアンサー「No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」に記載されているのですが、「利用価値が著しく低下している宅地」と表現されており、「高低差がある土地」とは表記されていません。
なお、高低差のある宅地以外には、地盤に甚だしい凹凸のある宅地や、震動の甚だしい宅地などが含まれます。さらに、土地の形状による利用価値の低下以外にも、騒音や日照阻害、臭気、忌みなど、売買する際の取引金額に影響を及ぼすことが認められるものがその対象となっています。
以前のコラムでもこの「利用価値が著しく低下している宅地の評価 」について記載をしています。本記事と併せて読み返していただければ幸いです。
▶関連記事はこちら「近くに墓地があると土地の評価は下がるのか!?」
2.高低差がある土地と判断される基準
高低差がある土地に該当するかの判断基準は次の2つです。各要件を満たしている場合に限り、高低差のある土地として認められることとなります。
- 評価対象地と道路の高低差がどの程度あるのか
- 土地の高低差の影響が路線価に反映されているか
1. 評価対象地と道路の高低差がどの程度あるのか
土地の高低差は、道路と接している部分の高さで判断しますが、高低差の判定の目安の高さは地域ごとに異なります。国税不服審判所の裁決を見ていくと、高低差が平均1.2mで「利用価値が著しく低下している宅地」と判断された事例がある一方で、高低差3m以上の土地でも高低差による利用価値が著しく低下しているとは認められなかった事例もあります。そのため、「道路との高低差が何m以上なら、高低差のある土地として減額補正を適用できる」という具体的な数値は明言できず、高低差があるということは最低限の基準になるだけなのです。
そこで重要になるのが、2つ目の判断基準「高低差の影響が路線価に反映されているか」という点です。
2. 土地の高低差の影響が路線価に反映されているか
高低差のある土地に該当する場合の減額は、適切な評価額を算出するための補正処理の一つですが、地域によっては高低差により生じる価額の補正処理が路線価に織り込まれている場合があります。路線価に高低差の影響が加味されていれば、評価対象地とその路線価が設定されている道路に高低差があったとしても、「利用価値が著しく低下している宅地」の減額補正は適用できません。
道路との高低差が3m以上ある場合でも国税不服審判所が減額補正を認めなかったケースもありますが、これは路線価に高低差の影響が織り込まれていると判断したからです。
路線価に土地の高低差による影響が加味されているどうかは、評価対象地の周辺地域の状況や周辺で設定されている路線価の金額の違いを比較することで判断できます。段差や傾斜地の多い地域の場合、評価対象地の周辺地域全体に高低差による路線価の調整が行われていると想定されるためです。
路線価は税務署の担当職員が毎年金額設定をしていますが、路線価の設定方法については対外的に公表されていません。したがって、高低差のある土地の減額補正を適用する際は、評価対象地と周辺地域の状況と路線価を照らし合わせ、高低差による影響が路線価に加味されているかを判断する必要があります。
3.路線価によらない方法とその注意点
ここまで、高低差がある土地で利用価値が著しく低下していることを認められるかどうかを解説してきました。しかし、10%の減額補正しか適用できないことに、高い効果を見いだせないという方もいるかと思います。
高低差がある土地を含む「利用価値が著しく低下している宅地の評価」について、算出した相続税評価額と実勢価格が乖離していることを理由に、路線価方式以外の方法で評価額を計算することもできます。
相続税で土地を評価する場合、原則は路線価方式、路線価地域以外は倍率方式で評価額を計算します。しかし、財産評価基本通達では、通達の定める方法で評価することが著しく不当であると認められる場合、路線価方式や倍率方式以外の方法で評価額を算出することを認めています。著しく不当と認められるのは、路線価方式による評価額と、評価対象地を売買する想定での取引価格の差が大きい場合が挙げられます。
路線価によらない方法の例としては、評価対象地の周辺地域の売買実例を調べることや、不動産鑑定士に鑑定を依頼したりする方法などがあります。
路線価は、その年に発生したすべての相続・贈与の計算で用いることを想定しており、1年間の地価変動にも耐え得る価額として設けられています。そのため、路線価方式による評価額が評価対象地の価値を正しく算出していないことを説明する必要があります。取引相場よりも高いとの理由のみでは、これらの方法で評価することはできませんので、ご注意ください。
図面上でも高低差の記載はあるのですが立体的な視点では描かれていないことも多いため、高低差の認識は普段からお使いになっている方以外見落としがちになります。
それでもこのように減額を行うことも可能であることを今回のコラムで知っていただくことでご自身の土地評価に関して関心を持っていただければ幸いです。
▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら
おすすめ勉強会
この記事の執筆者紹介
岡田 祐介
ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

.png)